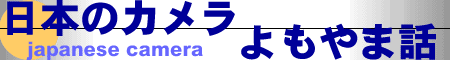
第3回
デジカメ全盛の現代に、戦後の
国産二眼レフの新鮮な魅力を発見!

一方で旧カメラ人類の私などは、仕事が多忙なジジイなので、逆にデジカメの比率が増えている。現像に出して、それをピックアップして、今度はその選んだフィルムを編集部に届けるという複雑な時間と手間がいる。にもかかわらず、一般に原稿料は安いから(これは本稿を当てつけに言っているのではない。キタムラさんからは結構なギャラを頂戴しております)時間の節約の為に、(フィルム代の節約ではない。フィルム代は写真家の経費の中ではわずかなものである)デジカメで撮影して、インターネットで画像を送稿というのが、普通だ。私の朝日新聞の連載記事「カメラアイ」もそうだし、この連載もシステムは同様である。
二眼レフは、真面目な写真家の武器なのである。かの、ライカ名人木村伊兵衛先生も、ここ一番!と撮影の気合いを入れる時には、ローライフレックスを愛用したし、名作「11時02分ナガサキ」の東松照明さんは、ミノルタオートコードを愛用した。石元泰博さんは、アメリカのニューバウハウス出身の英才であるが、ローライフレックスを愛用する一方で、1960年代の日本製二眼レフの優秀さを激賞している。
事実、1950年代から60年代にかけて、この国は二眼レフ天国であった。それはカメラファンのローライフレックスへの渇望が生んだのである。戦後、開発途上国であったこの国にとって、ローライはその価格からしても、一般写真愛好家にとっては、それは高嶺の花であるどころか、それを購入することを想像することも不可能な高級カメラであった。
