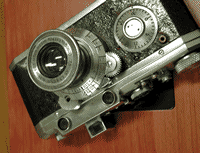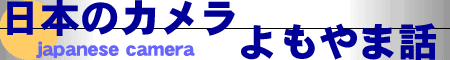
最終回
日本の「らいか」と日本の「こんたっくす」
戦前、戦後の日本の距離計カメラを旅する。

たなか ちょうとく/1947年東京生まれ、日大写真科卒。日本デザインセンター勤務の後、1973年からフリーランス写真家に。ウィーンに8年間、ニューヨークに1年間滞在。東京、ウィーン、ニューヨークなどで個展多数開催。著書・写真集多数。最近はクラシックカメラのエッセイの仕事も多い。日本写真家協会会員。
撮影:中村文夫氏
世の中はデジカメ一色の感がある。私のようなオールドライカボーイでも、仕事に使うカメラは現在では完全にデジカメに頼っている。ところが一方で、趣味の写真と言うべきか、あるいは、純粋な写真芸術の方面と言うべきか、その言い方はいろいろあろうが、要するに自分の楽しみの為の写真というのは、ライカを始めとするレンジファインダー機で撮影をしているのだ。
実例を挙げれば、私がライカM2を購入したのは1967年、つまり私は1947年生まれであるから、ちょうど二十歳の時のことで、それ以来、M2をずっと自分の写真行為の最前線で使用しているのだ。